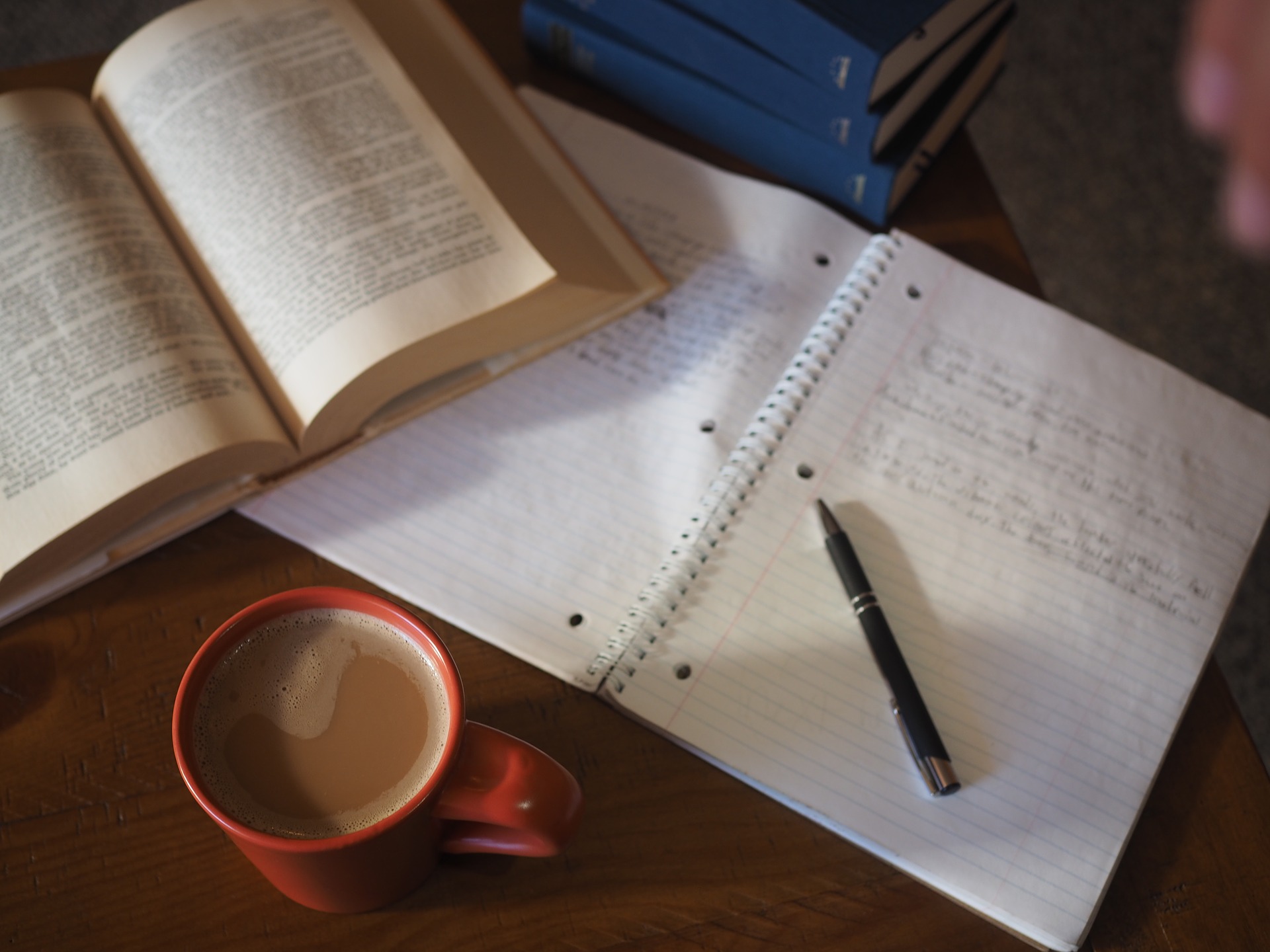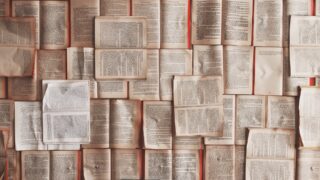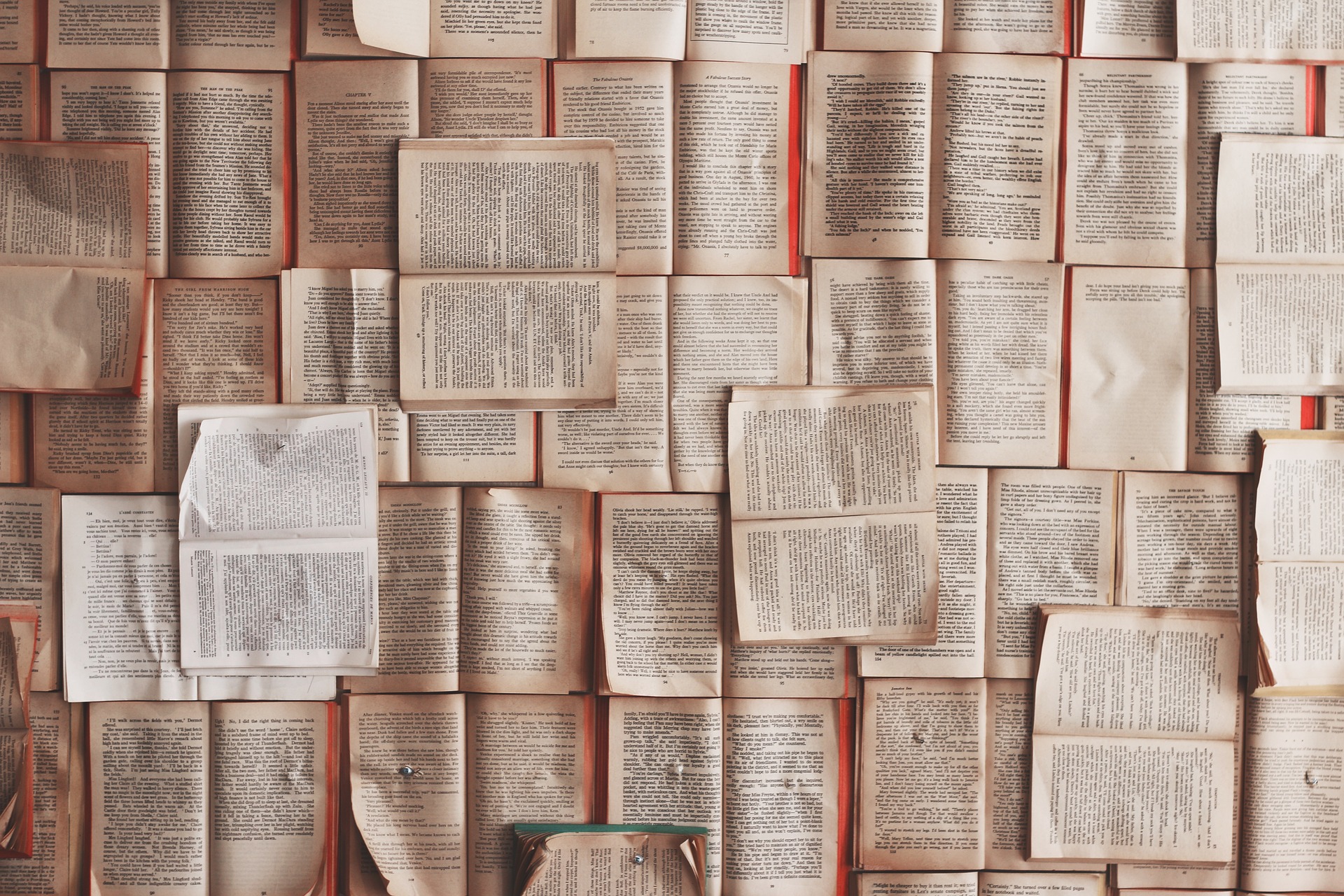こんにちは、バニラアイスです。
以前、証券外務員試験に合格するための勉強方法として、「1. 配点の高い出題科目を制覇する」「2. 得点源の5択問題を中心に勉強する」「3. 過去問をひたすら解く」という3つを挙げました。
今回からは、それらの中でも最も効率よく出来る「5択問題」についての解説を行っていきます。
もし勉強方法の記事をご覧になってなければ、こちらからどうぞ。
なお、今回の記事はフィナンシャルバンクインスティチュート製作の『うかる証券外務員』シリーズの分析を基に執筆しています。
証券外務員の勉強で最も使われているテキストなので、このシリーズだけを購入していれば十分に合格できます。
▼必修テキスト
▼問題集

証券外務員のテキストは沢山見たけど、一番分かりやすいと思ったのがこのテキストです(;・∀・)
見出し
外務員試験の5択問題について
では本題に入る前に、試験の出題範囲についておさらいをしましょう。
既に以前の記事でも書きましたが、外務員試験の5択問題の比率は非常に高くなっています。
合格基準が70%なのに対し、5択問題の点数比率は約68%となり、5択問題だけ勉強しても試験に合格してしまうほどです。
実際に5択問題の出題範囲については以下の表の一番右の部分をご覧ください。
▼外務員試験の配点表
| 一種出題科目 | 配点 | ○×問題 | 5択問題 | |
| 1 | 金融商品取引法 | 32点 | 12点 | 20点 |
| 2 | 金融商品の勧誘・販売に関係する法律 | 6点 | 6点 | — |
| 3 | 協会定款・諸規則 | 46点 | 16点 | 30点 |
| 4 | 取引所約款・諸規則 | 12点 | 12点 | — |
| 5 | 株式業務 | 52点 | 12点 | 40点 |
| 6 | 債権業務 | 40点 | 10点 | 30点 |
| 7 | 投資信託及び投資法人に関する業務 | 34点 | 14点 | 20点 |
| 8 | 付随業務 | 10点 | — | 10点 |
| 9 | 証券市場の基礎知識 | 10点 | — | 10点 |
| 10 | 株式会社法概論 | 20点 | 10点 | 10点 |
| 11 | 経済・金融・財政の常識 | 20点 | — | 20点 |
| 12 | 財務諸表と企業分析 | 20点 | 10点 | 10点 |
| 13 | 証券税政 | 22点 | 12点 | 10点 |
| 14 | セールス業務 | 10点 | 10点 | — |
| 15 | 先物取引 | 42点 | 2点 | 40点 |
| 16 | オプション取引 | 34点 | 4点 | 30点 |
| 17 | 特定店頭デリバティブ取引等 | 30点 | 10点 | 20点 |
| 合計 | 440点 | 140点 | 300点 |
5択問題と聞くととても難しそうな印象を受けますが、実際には毎年出題される問題が非常に似通っているので、勉強さえしていれば楽に点数を稼ぐことが出来ます。
銀行や証券会社の職員が持っていないと仕事ができないという特性上、難易度もそれほど高くありません。過去問からの焼き直し問題も多く、出題される問題もある程度推測されるようになっています。
例えば今回解説する「金融商品取引法」で出題される5択問題は2問ですが、参考書などで出題が予測されている問題はたったの4問です。
僕自身〇×問題はほぼスルーして5択問題に注力して合格したので、ここさえしっかりと勉強できていれば軽く合格することができます。
暗記が中心の〇×問題と比較すると内容は難しくなりますが、重要な得点源である以上しっかりと勉強することが大切です。
金融商品取引法(例問:4問・出題数:2問)
〇×問題:12点 5択問題:20点
俗に「金商法」と呼ばれる部分ですね。以下の3つの内から出題されます。
▼金融商品取引法での5択問題の出題範囲
② 内部者取引
③ 情報開示制度
これからそれぞれの例題を出して、わかりやすく解説を行っていきます。
有価証券の媒介、取次ぎ、代理について
始めに証券会社の取引形態についてです。
あまり一般的には馴染みがないと思いますが、顧客のお金を株式に変えて運用するだけが証券会社の仕事ではありません。
顧客の名義で取引をすることもあれば、証券会社自身の名義で取引を行うこともあります。
ここで重要なのが、「誰のお金」「誰の名義」で運用するかという2点です。
問題①
「有価証券の売買の媒介、取次ぎ及び代理」に関する記述として正しいものの番号を1つ選びなさい。
1 媒介とは、委託者の計算で自己の名で有価証券を売買すること等を引き受けること。
2 媒介とは、委託者の計算で委託者の名で有価証券を売買すること等を引き受けること。
3 取次ぎとは、委託者の計算で自己の名で有価証券を売買すること等を引き受けること。
4 取次ぎとは、委託者の計算で自己の名で有価証券を売買すること等を引き受けること。
5 代理とは、委託者の計算で自己の名で有価証券を売買すること等を引き受けること。
解説
正解:4
▼媒介、取次ぎ、代理の説明
| 媒介 | 他人間の取引の成立に尽力すること |
| 取次ぎ | 委託者の計算で、自己の名で有価証券の売買などを引き受けること |
| 代理 | 委託者の計算で、委託者の名で有価証券の売買などを引き受けること |
ここは厳密に覚えるのではなく、「媒介」「代理」などの言葉の意味から連想できるようになるといいです。
この「媒介、取次ぎ、代理」について、これらは全て顧客のお金を使っています。
証券会社自身のお金を使うようになれば、それは自己取引と言われます。
ちなみに外務員試験で頻出する「委託者の計算」という言葉はあまり見慣れないものだと思います。
この「計算」とは「お金」という言葉とほぼ同義です。代理(委託者の計算で、委託者の名で取引を行うこと)だと委託者のお金と名義で取引をするという意味ですね。

言葉の意味を覚えればいいんだね!
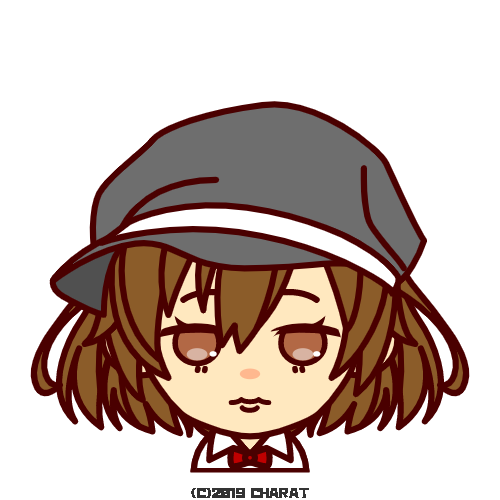
内部者取引について
内部者取引とは、会社関係者が会社の重要事実を知って、その重要事実が公表されて一定の時間が経つ前に、当該会社の株式の売買を行ってはならないというものです。
簡単に言うと、会社の関係者が職務上に知りえた重要事実を使って株で儲けてはならないということです。
内部者取引の学習内容は主に①会社関係者の範囲、②重要事実の種類、③重要事実の公表期間、④内部者取引の適用除外の4つがあります。
この中でも①、②の部分が5択問題では頻出なので、ここで解説を行っていきます。
問題②
内部者取引の要件としての会社関係者に範囲に該当しないものを選びなさい
1 その上場会社の役員、代理人、従業員
2 その上場会社の帳簿閲覧権を有する株主
3 その上場会社と契約を締結している者(取引銀行や公認会計士など)
4 以前に会社関係者であり、離職して2年経過している者
5 その会社関係者より情報の伝達を受けた第一次情報受領者
解説
正解:4
会社関係者でなくなってから1年が経過したものは会社関係者とはなりません。
この論点は4番の選択肢(以前会社の関係者であり、現在は既に離職している者)の内容が誤りとして出やすいです。数字が出ているのでここが一番変えやすいですからね。
特に数字を1年から「1年半」や「2年」に変更されて出題される場合が非常に多くあります。
試験に出た場合は真っ先に確認してみると、悩まなくて済む場合があるでしょう。
▼試験に出やすい『会社関係者の主な範囲』
②帳簿閲覧権を有する株主
③会社と契約を締結している取引銀行、公認会計士、弁護士など
④会社を辞めて1年以内の者(1年を超えてからは会社関係者に該当しない)
⑤会社関係者から情報の伝達を受けた第一次情報受領者
会社と関係がありそうなものは大体「会社関係者」です。
フィーリングで判断できるので、詳しく覚える必要はありません。
問題③
内部者取引における業務に関する重要事実に該当しないものを選びなさい
1 主要株主(議決権の100分の10以上所持)の異動
2 新製品および新技術の開発
3 合併、会社の分割
4 資本金の額の減少
5 役員の解任・辞職
解説
正解:5
続いて内部者取引における重要事実についてです。重要事実については子会社に起こったものも含まれるのでご注意ください。
また、一度行うと決定した事実を覆した場合も重要事実に該当します。本来行うはずだったことを取りやめにした場合は、会社の株式や債券を購入している投資家にも損害が及ぶ可能性があるからですね。
この重要事実は量が多く全て覚えようとすると時間がかかるので、参考書の模擬問題などを見て該当しないものを覚えるようにしましょう。

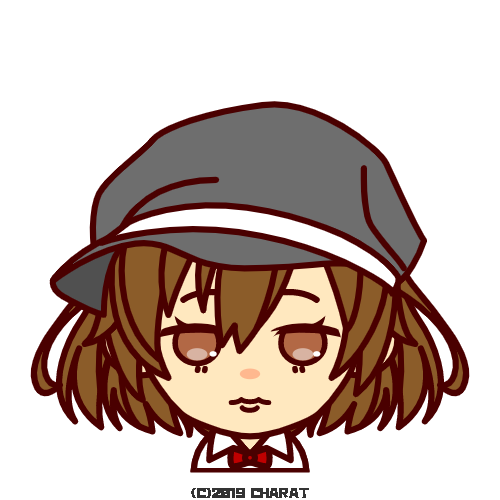
情報開示制度
情報開示制度とは、一般投資家が十分な投資判断ができるように決められた制度です。
いざ投資を行おうとしてもその企業の財務状況や経営成績に関するデータが手に入らないと正しい投資判断ができないので、株式によって資金調達を行う会社は正しい情報を投資家に開示しなければなりません。
この情報開示制度の論点で5択問題として出やすいのは、「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」で、一般的に5%ルールと呼ばれている部分です。
問題は覚えやすく得点源として有名な箇所なので、点数を取れるように勉強しておきましょう。
問題④
次の「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」を読み、( )の中に入る正しい選択肢を選びなさい。
上場会社などが発行する株券の保有者で、その保有割合が( ア )%を超える者は大量保有者となった日から( イ )日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書を提出し、発行者にその写しを報告する義務がある。この報告書は( ウ )年間公衆の縦覧に供される。
また、大量保有者の株券保有割合が( エ )%以上増減するなど、重要な変更事項が起こった際には、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1 ア:1 イ:5 ウ:5 エ:5
2 ア:5 イ:1 ウ:5 エ:1
3 ア:5 イ:5 ウ:5 エ:1
4 ア:5 イ:1 ウ:5 エ:5
5 ア:5 イ:5 ウ:1 エ:1
解説
正解:3
ちなみに株券等を共同保有する場合には、保有者全員の合計を1つとして扱われるので、ここも注意が必要です。
Aさん 3%
Bさん 2%
Cさん 1%
上記の3人が共同保有者だった場合、3人の株券を合計した6%が保有率となり、5%ルールが適用されて報告書を提出しなければなりません。

覚えやすくていいね!
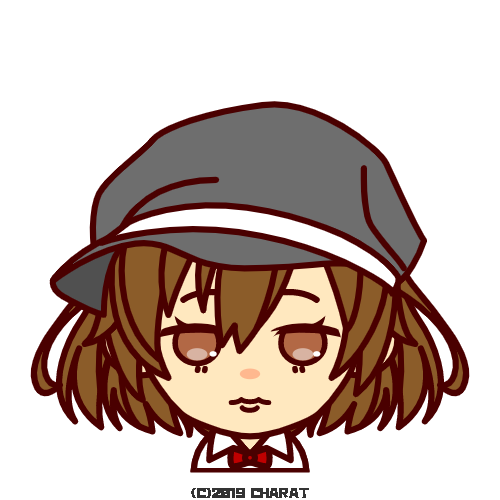
まとめ
では、証券外務員一種の5択問題の解説【金融商品取引法編】はこれまでです。
過去問の解説はいかがでしたか? 案外あっさり終わって拍子抜けしている方も多いのではないでしょうか。
今回勉強した場所が全て分かっていれば、20点は確実に取ることが出来ます。
これから重要な箇所は全て解説を行っていくので、あなたの勉強の一助になれることを願っています。
では、次回の【協会定款・諸規則】でお会いしましょう!

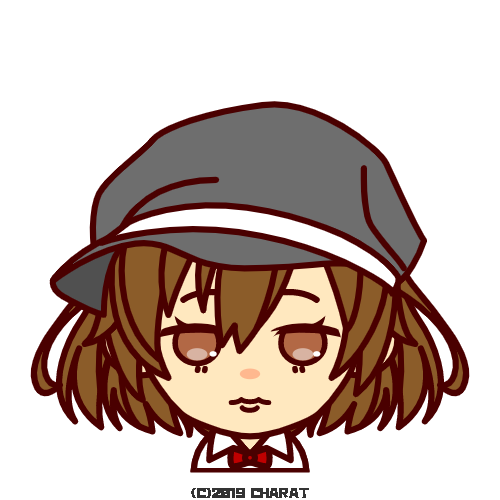
▼次回